是枝さんに特注して作っていただいた6336Bppアンプも、Oさんの三号機を入れると三台揃いました。戻って来た一号機は、6336Bの双極管の揃いの問題で、片側づつピッタリ揃えるために、バイアス電源を独立して揃えられるように、改良していただいた新しいヴァージョンです。同じ設計、製作者でも、真空管が違ったり、使用しているコンデンサーや抵抗の種類によっても音が変わります。配線の微妙な差も音の違いに出るのが、アンプの面白さでもあり、怖さでもあります。
レーシングカーも、同じ設計で作っても微妙に個体差がでてくるのは仕方がありません。今回は、トランスカバーの色も違い、それによる音の差も現れてくるようです。
![]()
一号機の改造中は、赤のトランスカバーの二号機を使っていました。音が濃く、立体感も良く出ます。その音に合わせて、電源ケーブルやインターコネクトも合わせて使っていました。
![]()
一号機の改造が終わったので、その二号機の替わりに先週から鳴らしています。音は二号機と違い、随分と地味です。しかし、その一号機の特性にあわせて音を追い込んでいくと、低域の豊かさが一番あるのが解ってきます。バイアスの調整も、電流値の変化にも、敏感に変わっていくのです。70mAから80mAの間で2mAぐらいずつ音がはっきり変わっていくのが解ります。ダンピングファクターコントロールが一番近い機能でしょうか。
![]()
そしてOさんの、黄色いカバーの三号機です。まだ改良前ので、右側のアンプの一つが、75mA以下になりません。当初は良いのですが、2〜3時間使い込んでいくと、全体に電流が流れ、熱く濃い音になっていきます。音量の変化には、余り変わりません。そのあたりの調整を是枝さんにお願いする予定です。
同じアンプなのに、音は三台とも違います。ねずみ色の一号機は、最低域の再現性は、凄いですが、全体には地味な感じ。クラシックを聴くには聴きやすいかも知れません。赤の二号機は、真空管の特性も合っていて、一番ダイナミックな展開をします。電流値の変化にも大きく反応します。インピーダンスが低くなる大音量時には、バイアス電流値もそれに追従して上がり、ダイナミックレンジも大きく変化して、普通のアンプとは活性度が随分と違います。Oさんのアンプは、まだ鳴らし込みが若い感じがしました。電源ケーブルの色を黄色からみどりに変えると、音のダイナミクスががらりと変わり、奥深い音になります。両方とも是枝さん推奨のカラーです。面白いですね。
![]()
三台の比較試聴は、いつものショスタコヴィッチの15番。これほどいろいろな楽器がでてくるCDも滅多にありません。
![]()
サンサーンスのオルガン付きの第三番は、二楽章ばかり聴いています。最近、このCDがどこかに紛れて探したのですが、解りません。焦って、アメリカに発注しました。それが到着したら、いつもは聴かないCDの中に紛れ込んでいました。同じ盤ですが、微妙に音は違います。
![]()
最近手に入れた、PHILIPSの初期盤です。極めてアナログ的な、自然で良い音がします。
![]()
スタジオ録音の典型ですが、バックの演奏が好きです。
Oさん 昨日の配置から、SPの間隔を6センチ拡げました。間隔が狭いと、ほんの少しの差が、大きな変化になります。中央で聴くと、自由度がないように思いました。いつもは右端で聴いているから余り気にしなかったのですが、少し窮屈な感じがしました。一旦動かすと、またバランスを取るのが、大変です。寸法の計測は、そこからどのくらい差があるか、調整時の目安です。また、寄ってください。
レーシングカーも、同じ設計で作っても微妙に個体差がでてくるのは仕方がありません。今回は、トランスカバーの色も違い、それによる音の差も現れてくるようです。

一号機の改造中は、赤のトランスカバーの二号機を使っていました。音が濃く、立体感も良く出ます。その音に合わせて、電源ケーブルやインターコネクトも合わせて使っていました。

一号機の改造が終わったので、その二号機の替わりに先週から鳴らしています。音は二号機と違い、随分と地味です。しかし、その一号機の特性にあわせて音を追い込んでいくと、低域の豊かさが一番あるのが解ってきます。バイアスの調整も、電流値の変化にも、敏感に変わっていくのです。70mAから80mAの間で2mAぐらいずつ音がはっきり変わっていくのが解ります。ダンピングファクターコントロールが一番近い機能でしょうか。

そしてOさんの、黄色いカバーの三号機です。まだ改良前ので、右側のアンプの一つが、75mA以下になりません。当初は良いのですが、2〜3時間使い込んでいくと、全体に電流が流れ、熱く濃い音になっていきます。音量の変化には、余り変わりません。そのあたりの調整を是枝さんにお願いする予定です。
同じアンプなのに、音は三台とも違います。ねずみ色の一号機は、最低域の再現性は、凄いですが、全体には地味な感じ。クラシックを聴くには聴きやすいかも知れません。赤の二号機は、真空管の特性も合っていて、一番ダイナミックな展開をします。電流値の変化にも大きく反応します。インピーダンスが低くなる大音量時には、バイアス電流値もそれに追従して上がり、ダイナミックレンジも大きく変化して、普通のアンプとは活性度が随分と違います。Oさんのアンプは、まだ鳴らし込みが若い感じがしました。電源ケーブルの色を黄色からみどりに変えると、音のダイナミクスががらりと変わり、奥深い音になります。両方とも是枝さん推奨のカラーです。面白いですね。
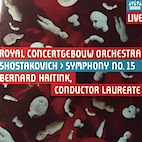
三台の比較試聴は、いつものショスタコヴィッチの15番。これほどいろいろな楽器がでてくるCDも滅多にありません。
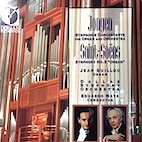
サンサーンスのオルガン付きの第三番は、二楽章ばかり聴いています。最近、このCDがどこかに紛れて探したのですが、解りません。焦って、アメリカに発注しました。それが到着したら、いつもは聴かないCDの中に紛れ込んでいました。同じ盤ですが、微妙に音は違います。
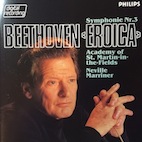
最近手に入れた、PHILIPSの初期盤です。極めてアナログ的な、自然で良い音がします。
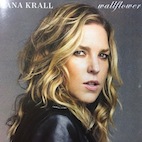
スタジオ録音の典型ですが、バックの演奏が好きです。
Oさん 昨日の配置から、SPの間隔を6センチ拡げました。間隔が狭いと、ほんの少しの差が、大きな変化になります。中央で聴くと、自由度がないように思いました。いつもは右端で聴いているから余り気にしなかったのですが、少し窮屈な感じがしました。一旦動かすと、またバランスを取るのが、大変です。寸法の計測は、そこからどのくらい差があるか、調整時の目安です。また、寄ってください。
















