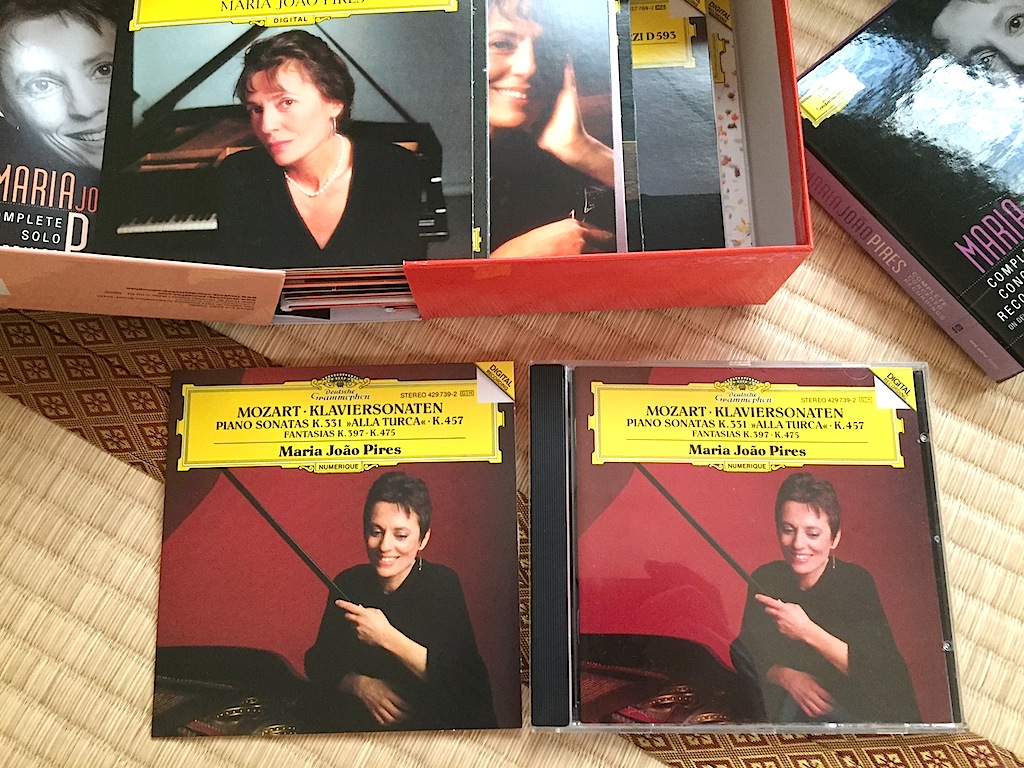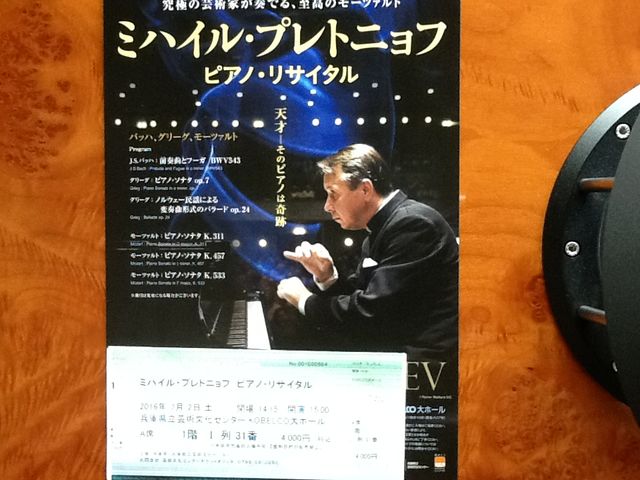土曜日の昼間、秋葉原のHさんのお宅に出かけるとき、今日の演奏会はどうするのと、家人に訊かれました。ん?そうか、今日は紀尾井の定期公演なのかと思い出しました。Hさんのお宅から回ることになりますので、最初の曲は間に合わないでしょう。
案の定、第一曲のブリッジの弦楽のための組曲は間に合いませんでした。二曲目のベルトのタブラ・ラサは不思議な曲でした。静かに同じ旋律を繰り返していく中に、弦にネジを挟んだと言われるプリペアドピアノの妙な音色が挟まります。不協和音が響き渡るクライマックスを越えると、同じ旋律がしずかに繰り返されていく曲で、ふ〜んという感じはしましたが、中途半端な気持ちになりました。先日のヒラリー・ハーンの後半みたいな演奏者は面白いのかもしれませんが、保守的な聴衆には、消化不良の感もあります。
休み時間は、久し振りにNextNextさんの奥さまにお会いしました。今日はご自身は洋装で、和装のご友人と来られていました。ご主人のNextNextさんも、一年間の大学院も終わってそろそろ復帰されるそうです。ご主人にお会いしたいですね。また、ご一緒に遊びに来てください。
さて、後半は、ドヴォルザークの弦楽セレナードです。こちらは、よく聴いてきた名曲です。カラヤンの名演がありますが、最近は聴いたことがありません。誰の演奏で聴いたのだろうと考えていました。小澤さんとサイトウキネンかも知れません。それとも、オルフェウスか・・・
こちらは名演でした。先日の水戸の演奏にも劣らない、バランスと柔らかい中にも力強さを秘めた演奏でした。アンコールは、カバレリア・ルスティカーナの間奏曲でした。終わってみると、リーダーのバラホフスキーのやさしさがでた演奏会でした。紀尾井シンフォニエッタ東京という名も今回で終わり、次回からは、紀尾井ホール室内管弦楽団という名前になるそうです。相変わらず長い名前ですね。紀尾井室内管弦楽団で良いと思うのですが、、、
今日は、ベルウッドさんは来られていませんから、恒例の反省会はありません。日がすっかり長くなった真田堀の横の道をすっかりと色づいた紫陽花をたのしみながら帰って来ました。
![f0108399_16415350.jpg]()
![f0108399_16421369.jpg]()
![f0108399_16422726.jpg]()
![f0108399_16424124.jpg]()
案の定、第一曲のブリッジの弦楽のための組曲は間に合いませんでした。二曲目のベルトのタブラ・ラサは不思議な曲でした。静かに同じ旋律を繰り返していく中に、弦にネジを挟んだと言われるプリペアドピアノの妙な音色が挟まります。不協和音が響き渡るクライマックスを越えると、同じ旋律がしずかに繰り返されていく曲で、ふ〜んという感じはしましたが、中途半端な気持ちになりました。先日のヒラリー・ハーンの後半みたいな演奏者は面白いのかもしれませんが、保守的な聴衆には、消化不良の感もあります。
休み時間は、久し振りにNextNextさんの奥さまにお会いしました。今日はご自身は洋装で、和装のご友人と来られていました。ご主人のNextNextさんも、一年間の大学院も終わってそろそろ復帰されるそうです。ご主人にお会いしたいですね。また、ご一緒に遊びに来てください。
さて、後半は、ドヴォルザークの弦楽セレナードです。こちらは、よく聴いてきた名曲です。カラヤンの名演がありますが、最近は聴いたことがありません。誰の演奏で聴いたのだろうと考えていました。小澤さんとサイトウキネンかも知れません。それとも、オルフェウスか・・・
こちらは名演でした。先日の水戸の演奏にも劣らない、バランスと柔らかい中にも力強さを秘めた演奏でした。アンコールは、カバレリア・ルスティカーナの間奏曲でした。終わってみると、リーダーのバラホフスキーのやさしさがでた演奏会でした。紀尾井シンフォニエッタ東京という名も今回で終わり、次回からは、紀尾井ホール室内管弦楽団という名前になるそうです。相変わらず長い名前ですね。紀尾井室内管弦楽団で良いと思うのですが、、、
今日は、ベルウッドさんは来られていませんから、恒例の反省会はありません。日がすっかり長くなった真田堀の横の道をすっかりと色づいた紫陽花をたのしみながら帰って来ました。