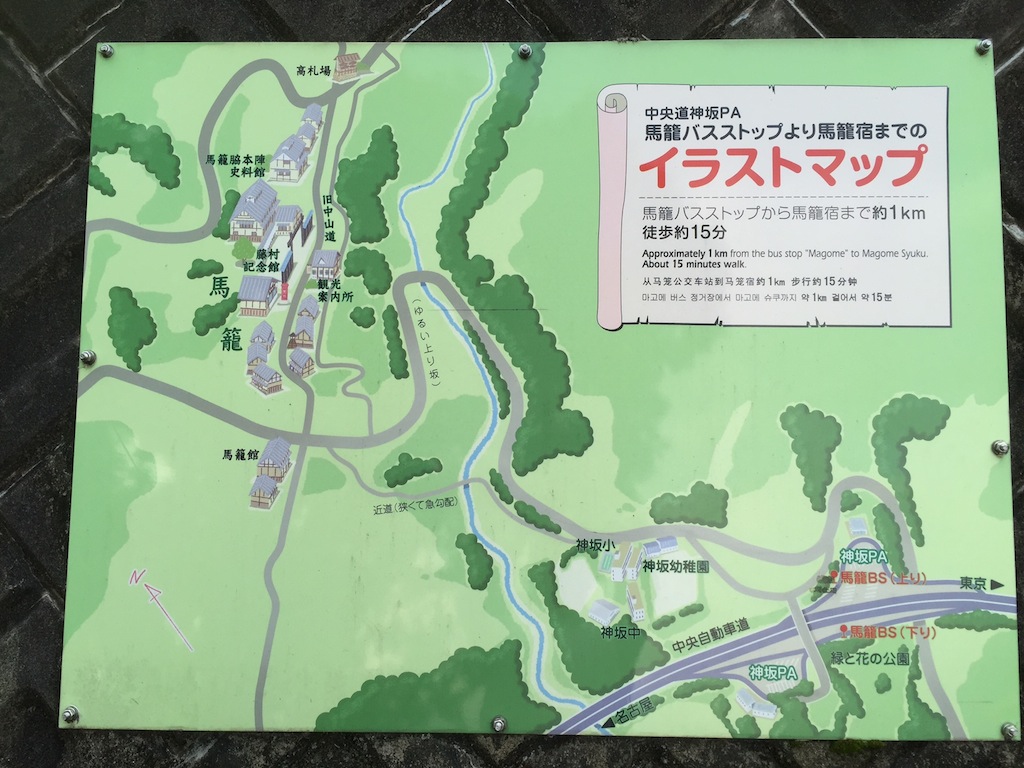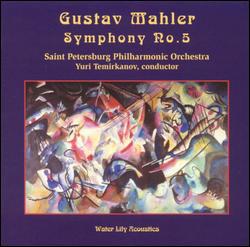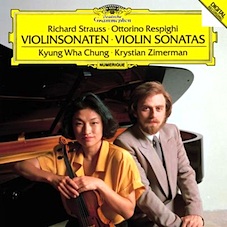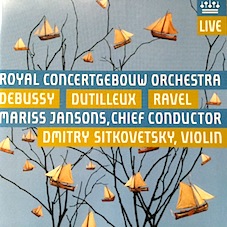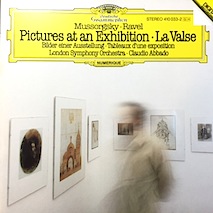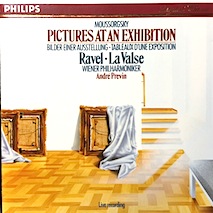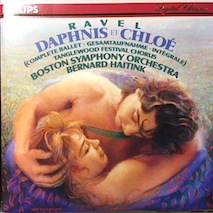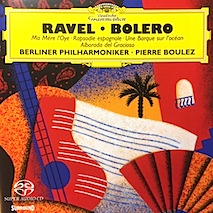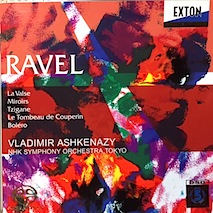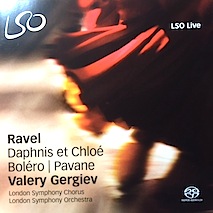先日、Aionさんとご一緒に、お越しいただいた i さんの画廊に、夕方お邪魔致しました。先日お話しをした作家の絵を見に行くためです。25年以上も親しんできた絵画ですが、ようやく機が熟してきた感じがしたからです。i さんの画廊は、現代絵画がご専門です。i さんお目を通した確かな作品は、日本中の美術館のコレクションにもなっていて、そういう美術館の若い文化員の教育や啓蒙、育成も長い期間掛けて継続しておられます。オーディオと同じ様に、物を見る目は簡単には得られません。良い作品を見続けるという経験を通じてでなければ、身につかないのです。
久し振りに i さんから美術界のお話しを聞いて、驚く事も沢山ありました。一番の驚きは、 i さんが、扱っておられた草間彌生さんの評価が世界中に広まり、特に中国での人気が上がったそうです。有名なカボチャをモチーフにした作品は、中国では縁起が良いと人気が高まり、作品が品薄になって高騰しているそうです。シルクスクリーンの作品でも自署のサインがあれば、信じられない程の価格がついていました。i さんの画廊での、草間さんの催し物が何回あり、i さんからご紹介いただいたこともありますので、その頃と現在のギャップに驚きました。
いつもながら、i さんのお話は、広く深く、半世紀に渡って、世界の美術界を生き抜いてこられた智恵と経験を聞かせていただくのは幸運だと思います。西に面した窓から西日が差しているので、時間が解りにくかったのですが、六時を回ってきたので、秋葉原のHさんお宅へ向かいました。Hさんのお宅へお伺いするのも、前回から一月も経っていました。ネジの緩みや地震の影響もあるかも知れませんので、今日は定期点検ですね(笑)。
![f0108399_1014462.jpg]()
早速、左右のチェックです。ピッタリ中央を差しています。地下のこの部屋は、しっかりとした土台の上に立っているので、殆ど影響は無かったようです。しかし、全体にピントが緩んでいる気がしました。低音が過剰なのです。左右のバランスはあっているのですが、奥行き方向が出て来ません。ウーファーの増し締めを行いました。角度にすれば15度ぐらいでしょうか、少し宛緩んでいました。一年中で一番湿気が多い頃です。新しい機器ですから、当然ですね。幾分良くなりましたが、以前として奥行き感が出ません。
足に注目してみました。前二つ、後ろ一つの三点支持に、中央の足を加えた四点で支えています。一点メカニカルアースを試みるため、その中央だけ1mm未満ですが高くなっています。その為中央以外の三点は、フェルトを挟んで、高さの調整をしていました。そのフェルトを外して見ることにしました。順位外すと、やはり中央の足が高く、ガタがでます。仕方が無いので、せっかく合っているトロバドールを一旦降ろして、SPを傾け中央の足を外しました。それから、再調整です。スッキリとしてきました。
再度、トロバドールの位置の微調整を行うと、低音の膨らみや、バランスが解消されて、音に奥行きと陰影が出て来ました。家と同じ傾向の音です。少し、暗かったHさんのお顔もみるみる晴れ晴れとしてきました。最近、オーケストラ物を聞いても楽しくなくなってきたようで、ピアノばかり聞かれてたようです。早速、ピリスのモーツァルトを掛けてみました。深々とステージが拡がり、ピアノの陰影や微妙なタッチが蘇ります。良い音です。
さっきまでの音とはまったく違い、コンサートホールが出現するのです。定番のハーディング・ウィーンフィルのマーラーの10番、第五楽章冒頭の大太鼓の音を聞いてみました。ステージの奥の方から、ホール全体に鳴り響く様が見えてきます。その後の弦楽器の美しいこと!鳴り方が、家と同じです。違いは部屋の環境ですね。カーテンや配置も考えて微調整していきましょう。
パトリシア・バーバーなどのJazzヴォーカルも聞いて音を確かめました。ハイティンクのチャイコフスキー第二番も、先程までとはまったく違うホール感です。増締めと、足のフェルトと、位置調整、ウーファーのケーブルを元に戻しただけですが、まったく違う音になりました。怖いと思います。ご自分の装置が、1〜2ミリ違うだけで、これほどまでの音の差が出るのですから。Hさんご自身にその違いをお話しして貰いましょう。
GRF様
昨日は、わざわざ、寄っていただきありがとうございました。最近は、やたらと地震が多いので、再調整してあげましょうかと、先日も、ご連絡して頂いたのですが、生憎、用事があったため実現出来ませんでしが、本日、実にタイミングよく来ていただくことができました。
GRFさんは、言わば私のオーディオの師匠なので、弟子のオーディオの具合を絶えず気にして下さっております。誠に有り難い限りです。
部屋に入って早速、ピントが合っているかどうかのチェックをして頂きました。ピントは、合っている、しかし何かがおかしいとの、師匠のご指摘でした。実は、最近、オーケストラの音が良くなくなっていたのでピアノばかり聞いておりました。スピーカーは、1mmも動かしていません。(笑 ) なのに、なぜか?自分でもだんだんオーケストラを聞かなくなっていることになっていたんですね。しかし、自分では、なかなか気づかなったんですね。そこで、師匠の診断が始まりました。
① SD05とCDプレーヤーの接続の確認されて、LRが逆でした。そういえば、先日、オープンテープを聞くために、一時抜き差ししていたのでした。その時、間違ってしまったのでした。見事に、指摘されました。
② 湿度の変化のためか、ウーファーのマス締め。すぐに、音色が変わりました。明るく表情豊かになりました。
③ それでも、納得いかないお師匠さんは、元のケーブルに交換。また、音の落ち着きが出てきました。
④ ウーファーの脚の下にフェルトを敷いていたのですが、取り去りました。その時、5点支持になっていたので、中央の脚を取りました。そして3点支持にしました。
最後に、再度、ピントの再調整をして頂きました。すると、どうでしょう。あのお師匠さんの家の音が、再現されてきたではありませんか!1ヶ月でこれほどまでに音の変化が、起こってしまうのか。このトロバドールとウーファーの組み合わせは、生きている!絶えず、微調整をしてあげないと、うまくなってくれないとつくづく思った次第です。まさに、成長の早い植物を育てているような感覚に襲われます。本当に来ていただいて良かったです。
今回は、お車だったので、ワインは、飲んでいただくことはできませんでした。再度、近々、いいワインをご用意してお待ちしております。そのコルクで、トロバドールとウーファーの間に敷物を作らないといけないので。よろしくお願い致します。ありがとうございました。
H
昨日は車でしたので、ワインの栓の輪切りの実験は出来ませんでしたが、最後の音は納得の音がしてました。音の出方、質感、音場感も家とそっくりでした。ただ、音量を上げると部屋の定在波の影響が出て来ますので、やはりその対策をしなければなりませんね。
良い音が出たので、iさんのご紹介で、池之端の洋食屋さんに出かけて、昔ながらの日本の洋食を頂きました。話も弾み、楽しい晩になりました。 i さんありがとうございました。Hさんは隠れ屋に戻られて、あのつづきを聞かれたことでしょう。
久し振りに i さんから美術界のお話しを聞いて、驚く事も沢山ありました。一番の驚きは、 i さんが、扱っておられた草間彌生さんの評価が世界中に広まり、特に中国での人気が上がったそうです。有名なカボチャをモチーフにした作品は、中国では縁起が良いと人気が高まり、作品が品薄になって高騰しているそうです。シルクスクリーンの作品でも自署のサインがあれば、信じられない程の価格がついていました。i さんの画廊での、草間さんの催し物が何回あり、i さんからご紹介いただいたこともありますので、その頃と現在のギャップに驚きました。
いつもながら、i さんのお話は、広く深く、半世紀に渡って、世界の美術界を生き抜いてこられた智恵と経験を聞かせていただくのは幸運だと思います。西に面した窓から西日が差しているので、時間が解りにくかったのですが、六時を回ってきたので、秋葉原のHさんお宅へ向かいました。Hさんのお宅へお伺いするのも、前回から一月も経っていました。ネジの緩みや地震の影響もあるかも知れませんので、今日は定期点検ですね(笑)。

早速、左右のチェックです。ピッタリ中央を差しています。地下のこの部屋は、しっかりとした土台の上に立っているので、殆ど影響は無かったようです。しかし、全体にピントが緩んでいる気がしました。低音が過剰なのです。左右のバランスはあっているのですが、奥行き方向が出て来ません。ウーファーの増し締めを行いました。角度にすれば15度ぐらいでしょうか、少し宛緩んでいました。一年中で一番湿気が多い頃です。新しい機器ですから、当然ですね。幾分良くなりましたが、以前として奥行き感が出ません。
足に注目してみました。前二つ、後ろ一つの三点支持に、中央の足を加えた四点で支えています。一点メカニカルアースを試みるため、その中央だけ1mm未満ですが高くなっています。その為中央以外の三点は、フェルトを挟んで、高さの調整をしていました。そのフェルトを外して見ることにしました。順位外すと、やはり中央の足が高く、ガタがでます。仕方が無いので、せっかく合っているトロバドールを一旦降ろして、SPを傾け中央の足を外しました。それから、再調整です。スッキリとしてきました。
再度、トロバドールの位置の微調整を行うと、低音の膨らみや、バランスが解消されて、音に奥行きと陰影が出て来ました。家と同じ傾向の音です。少し、暗かったHさんのお顔もみるみる晴れ晴れとしてきました。最近、オーケストラ物を聞いても楽しくなくなってきたようで、ピアノばかり聞かれてたようです。早速、ピリスのモーツァルトを掛けてみました。深々とステージが拡がり、ピアノの陰影や微妙なタッチが蘇ります。良い音です。
さっきまでの音とはまったく違い、コンサートホールが出現するのです。定番のハーディング・ウィーンフィルのマーラーの10番、第五楽章冒頭の大太鼓の音を聞いてみました。ステージの奥の方から、ホール全体に鳴り響く様が見えてきます。その後の弦楽器の美しいこと!鳴り方が、家と同じです。違いは部屋の環境ですね。カーテンや配置も考えて微調整していきましょう。
パトリシア・バーバーなどのJazzヴォーカルも聞いて音を確かめました。ハイティンクのチャイコフスキー第二番も、先程までとはまったく違うホール感です。増締めと、足のフェルトと、位置調整、ウーファーのケーブルを元に戻しただけですが、まったく違う音になりました。怖いと思います。ご自分の装置が、1〜2ミリ違うだけで、これほどまでの音の差が出るのですから。Hさんご自身にその違いをお話しして貰いましょう。
GRF様
昨日は、わざわざ、寄っていただきありがとうございました。最近は、やたらと地震が多いので、再調整してあげましょうかと、先日も、ご連絡して頂いたのですが、生憎、用事があったため実現出来ませんでしが、本日、実にタイミングよく来ていただくことができました。
GRFさんは、言わば私のオーディオの師匠なので、弟子のオーディオの具合を絶えず気にして下さっております。誠に有り難い限りです。
部屋に入って早速、ピントが合っているかどうかのチェックをして頂きました。ピントは、合っている、しかし何かがおかしいとの、師匠のご指摘でした。実は、最近、オーケストラの音が良くなくなっていたのでピアノばかり聞いておりました。スピーカーは、1mmも動かしていません。(笑 ) なのに、なぜか?自分でもだんだんオーケストラを聞かなくなっていることになっていたんですね。しかし、自分では、なかなか気づかなったんですね。そこで、師匠の診断が始まりました。
① SD05とCDプレーヤーの接続の確認されて、LRが逆でした。そういえば、先日、オープンテープを聞くために、一時抜き差ししていたのでした。その時、間違ってしまったのでした。見事に、指摘されました。
② 湿度の変化のためか、ウーファーのマス締め。すぐに、音色が変わりました。明るく表情豊かになりました。
③ それでも、納得いかないお師匠さんは、元のケーブルに交換。また、音の落ち着きが出てきました。
④ ウーファーの脚の下にフェルトを敷いていたのですが、取り去りました。その時、5点支持になっていたので、中央の脚を取りました。そして3点支持にしました。
最後に、再度、ピントの再調整をして頂きました。すると、どうでしょう。あのお師匠さんの家の音が、再現されてきたではありませんか!1ヶ月でこれほどまでに音の変化が、起こってしまうのか。このトロバドールとウーファーの組み合わせは、生きている!絶えず、微調整をしてあげないと、うまくなってくれないとつくづく思った次第です。まさに、成長の早い植物を育てているような感覚に襲われます。本当に来ていただいて良かったです。
今回は、お車だったので、ワインは、飲んでいただくことはできませんでした。再度、近々、いいワインをご用意してお待ちしております。そのコルクで、トロバドールとウーファーの間に敷物を作らないといけないので。よろしくお願い致します。ありがとうございました。
H
昨日は車でしたので、ワインの栓の輪切りの実験は出来ませんでしたが、最後の音は納得の音がしてました。音の出方、質感、音場感も家とそっくりでした。ただ、音量を上げると部屋の定在波の影響が出て来ますので、やはりその対策をしなければなりませんね。
良い音が出たので、iさんのご紹介で、池之端の洋食屋さんに出かけて、昔ながらの日本の洋食を頂きました。話も弾み、楽しい晩になりました。 i さんありがとうございました。Hさんは隠れ屋に戻られて、あのつづきを聞かれたことでしょう。