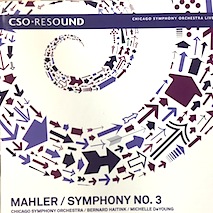新宿のオペラシティで、レイフ・オヴェ・アンスネスの指揮・マーラー・チェンバー・オーケストラと彼自身のピアノ演奏でベートーヴェンのピアノ協奏曲第二番、第三番、第四番を聴いてきました。2012年からベートーヴェン・ジャーニーと銘打って、世界中で演奏してきた三年間、60回にも及ぶ大プロジェクトの一環で、東京は54回と55回目にあたります。
マーラー・チェンバー・オーケストラは、ご存じの通り、クラウディオアバドが若手の教育機関として創設した若手の楽団のメンバーが集まって設立した45名程度のオーケストラです。アバドとルツェルンフェスティバルで活躍してきました。アバドの後、ダニエル・ハーディングがオーケストラを育て、現在は桂冠指揮者として活躍しています。今回のアンスネスはArtistic Partnerとして活動を最も共にしている演奏者でしょう。その他にも、コンセルトヘボウの常任指揮者になったダニエレ・ガッティやボストンのアンドリス・ネルソンスも振っています。
レイフ・オヴェ・アンスネスの名前は知っていましたが、一度もその演奏を聴いたことがありませんでした。曲目がベートーヴェンのピアノ協奏曲第二番、第三番、第四番の中身の濃いプログラムなので、それで引かれて行ったというのが正直なところです。そのピアノ協奏曲を世界中で演奏してきて完璧に出来上がった演奏を今日聴くことになります。
プロの演奏家は本当にすごい人達で、60回も集中して演奏する気力と根性に驚きます。「飽きない」のが「商い」の基本だとよく言われますが、良く集中が続く物だと感心しています。今までの演奏記録を見てみると、毎年、5月と11月に演奏旅行を行っているのが解ります。世界中の名だたるフェスティバルで演奏してきたことも、素晴らしい記録ですね。その間に熟成を重ねてきたようです。
![]()
オペラシティは久しぶりです。チョン・ミョンフンの演奏会とか、年一回やってくる山形管弦楽団とか、コジュヒンの素晴らしい演奏会もここでした。そういえばここでBellwoodさんにベイさんを紹介していただいたのです。最寄りの初台駅は、実際には都営地下鉄で、新宿駅では乗り換えが難しいのです。お上りさんで困ったことが何回もあったのです。実際には、新宿三丁目から乗り換えるのですね。
念のためインターネットで調べてみると、家からは、そばのバス停から渋谷駅のバスに乗るのが、時間も費用も手間もないことが解りました。渋滞に巻き込まれることもあるでしょうが、最近の環七は空いていますので、試して見ることにしました。家から最寄りのバス停は150メートルほどです。すると、すいすいと来てドアツウドアで30分以内で着きました。これは便利です!
この演奏会のことは、ベイさんの今月の演奏会の予定を拝見していて、良さそうだと思い、まだ売れ残っていた席を買い求めたのは一週間ほど前でした。偶然ですがそのベイさんは同じ列の五人ほど中央よりの席でした。Bellwoodさんは、二階席にいて、いつもと違う幾分よそ行きの表情をしています。理由は後から判明しました。
さて、ピアノ協奏曲の一曲目は第二番からです。五曲の中では、一番聴くことが少ない曲です。二番という番号になっていますが、この曲が実際は第一番ですね。ピアノ、フルート1、オーボエ2、ファゴット2、ホルン2、弦五部の構成で、室内楽の規模です。モーツァルトやハイドンの作曲と言われても納得する端正な曲です。演奏がはじまって驚きました。弦楽器の音が柔らかくとても豊かなのです。一階席の前の方からは、オーケストラ全員は見えません。
10.8.6.5.3の編成だと思われますが、ヴィオラとチェロ、そしてコントラバスの響きが、日本の室内オーケストラとはまったく違った豊かな響きなのです。いつも聴いている紀尾井や水戸の編成だと、8.6.4.4.2ですから、一回り大きな編成です。ヴィオラとチェロ、そしてコントラバスの暗い音もとてもバランスがよく、良く伸びた低音楽器の気持ちの良い響きがしてきます。弦楽器のボーイングが違うのか、力のかけ方が異なるのか、音が大きく、太く鳴りとても魅力的な響きです。
そして、アンスネスのピアノの音の柔らかく、透き通った響きにも驚きました。フタが無いので、音は天井に上がっていきます。オペラシティの天井は、教会の天井のように高く、徐々に減衰していきます。その会場とピアノの音がマッチして、素晴らしい音が出ていました。幾分線は細いのですが、余り聴いたことの無いピアノの音色です。女性的なタッチとでも言うのでしょうか、現代的な響きがします。柔らかく品が有ってとても良い演奏です。
曲が終わり大きな拍手に包まれている間に、フルート、クラリネット、トランペットそしてティンパニストが入場してきました。二曲目は、大好きな3番です。前回聴いたベートーヴェンの三番の協奏曲は、一昨年のコンセルトヘボウの演奏会でした。その時のヤンソンスの指揮での一糸乱れぬ演奏は、とても感心したことを覚えてきます。今日はどうだろうかと聴き始めたら、今参加してきた、トランペットとティンパニーの効果は目覚ましく、迫力の有るティンパニーの音が聞こえてきました。マレットは、堅い棒のタイプですが、革の厚みが違うのか、革の種類が違うのか、叩き方が迫力が有るのか、紀尾井シンフォニエッタの欲求不満のひ弱な音とは異なり、納得の迫力です。ティンパニーはトランペットとリズムを合わせて、アッチェランドしなければならないと感じました。そのトランペットも、ファンファーレで使うような幾分太いストレートなタイプでした。
ピアノも冴え渡っていきます。音がホールの上の方に昇華して立ち上っていきます。これと同じ経験をしたのは、もう、25年ぐらい前になりますが、ロンドンのフェスティバルホールで、ポリーニのショパンを聴いた時以来です。オーケストラは敬虔な祈りの様な柔らかな響きで、ピアノを支えていきます。二楽章のピアニシモの美しさには、会場全体が息をのむように聴いていました。ピアノ協奏曲の経験の中では、一番の演奏でしょう。オーケストラを熟成を重ねていき、ここまでの呼吸まで同じに出来る演奏は、そう有るものではありません。
聴いているとき、練習を重ねて自分の物にした、ツィーメルマンのショパンのコンチェルトを思い出しました。しかし、ショパンには無い、ベートーヴェンのオーケストレーションの凄さを感じました。オーケストラとピアノが対話を交わすのではなく、一体になっている演奏です。
この三番の演奏には、とても感動しました。終わった後の万雷の拍手には、演奏者にも伝わったことでしょう。今回の演奏ツアーは、香港、台湾、上海、ソウルと演奏を重ねてきました。しかし、東京の聴衆からこれだけの拍手を貰える演奏はそう有るものではありません。
休憩時間にこの感動を伝えたくて、いつものBellwoodさんを待っていましたが、二階の方のラウンジで飲まれていたそうです。いつもの様に二人分を、それも、めずらしくビールとワインを、一番多く次いでくれる係りを見付けて購入したのですが、当然来られなかったので、最後にワインは一気に飲みほしました。おかげで、第四番の低弦の音が少しだけ後退したように聞こえました(苦笑)。
その酔いの所為か、演奏の所為か、4番の一楽章は3番ほどの完成度では無かったように思いました。しかし、二楽章からぴたりとあって最後は、大きな感動の渦の中にいました。この演奏会に参加できて本当に良かったです。
終演後、感想戦で感動を分けあおうと期待していたのですが、今日は奥さまと同伴だそうで、いそいそ?と帰られました。今年の夏は、お二人でバイロイトの方までいかれるそうです。うらやましいです。
一人、甲州街道の横断歩道を渡って、暗いバス停で最終一つ前のバスを待っていたら、同じ演奏会から戻る方と乗り合わせました。その方は、途中の方南町あたりで下りられました。終点の少し前の下りる停留所まで乗っていたのは、数名でしたが、その内、四名ほど同じ停留所で降りられたのには、ビックリ。考えてみると、駅と駅の間の停留所で、このバスが便利なのかも知れません。帰りも30分ほどでした。
バスを降りてから、二つコーナーを曲がるとそこはもう家です。その短い間にも、今日の演奏の凄さ、ベートーヴェンの音楽の充実度、構成力、オーケストレーション、ピアノのスケールを目一杯使ったコストラックション、何よりも、音楽の純粋性を思い出していました。素晴らしい演奏会でした。
![]()
家に帰って調べると、60回にもおよぶ今回の公演の記録が、マーラー・チェンバー・オーケストラのホームページに乗っていました。
The Beethoven Journey
1. 15 May 2012 Bresia It. Beethoven Piano Concert no.1 & no.3
2. 16 May 2012 Lugano It. Beethoven Piano Concert no.1 & no.3
3. 17 May 2012 Torino It. Beethoven Piano Concert no.1 & no.3
4. 18 May 2012 Bergamo It. Beethoven Piano Concert no.1 & no.3
5. 20 May 2012 Dresden de. Beethoven Piano Concert no.1 & no.3
6. 22 May 2012 Prague cz. Beethoven Piano Concert no.1 & no.3
7. 23 May 2012 Prague cz. Beethoven Piano Concert no.1 & no.3
8. 25 May 2012 Bergen no. Beethoven Piano Concert no.1 & no.3
9. 14 Nov 2012 Regio Emilia Beethoven Piano Concert no.1 & no.3
10. 15 Nov 2012 Perugia It. Beethoven Piano Concert no.1 & no.3
11. 18 Nov 2012 Cologne de. Beethoven Piano Concert no.1 & no.3
12. 19 nov 2012 St. Poelten Beethoven Piano Concert no.1 & no.3
13. 20 Nov 2012 Birmingham Beethoven Piano Concert no.1 & no.3
14. 21 Nov 2012 Brussels be Beethoven Piano Concert no.1 & no.3
15. 24 May 2013 Bergen no. Beethoven Piano Concert no.2 & no.4
16. 16 Nov 2013 Neumarkt de. Beethoven Piano Concert no.3 & no.4
17. 17 Nov 2013 Landshut de. Beethoven Piano Concert no.2 & no.4
18. 18 Nov 2013 Brussels be. Beethoven Piano Concert no.2 & no.4
19. 20 Nov 2013 Edinburgh Beethoven Piano Concert no.2 & no.3
20. 21 Nov 2013 London uk Beethoven Piano Concert no.2 & no.4
21. 23 nov 2013 Basingstoke Beethoven Piano Concert no.2 & no.3
22. 24 Nov 2013 Dublin ie. Beethoven Piano Concert no.2 & no.4
23.16 May 2014 Regio Emilia Beethoven Piano Concert no.5 & others
24.18 May 2014 Turin it. Beethoven Piano Concert no.5 & others
25.19 May 2014 Lugano ch Beethoven Piano Concert no.5 & others
26.20 May 2014 Prague cz. Beethoven Piano Concert no.5 & others
27.23 May 2014 Bergen no Beethoven Piano Concert no.5 & others
28.24 Sep 2014 Hamburg de Beethoven Piano Concert no.2, no.3 & no.4
29.25 Sep 2014 Bonn de Beethoven Piano Concert no.2 & no.4
30.27 Sep 2014 Bonn de Beethoven Piano Concert no.3 & others
31.28 Sep 2014 Bonn de Beethoven Piano Concert no.1 & no.5
32.30 Sep 2014 Hamburg de Beethoven Piano Concert no.1 & no.5
33.24 Nov 2014 Lucerne ch Beethoven Piano Concert no.2, no.3 & no.4
34.26 Nov 2014 Lucerne ch Beethoven Piano Concert no.1 & no.5
35.01 Dec 2014 Vienna at Beethoven Piano Concert no.3 & others
36.02 Dec 2014 Vienna at Beethoven Piano Concert no.2 & no.5
37.04 Dec 2014 Brussels be. Beethoven Piano Concert no.5 & others
38.26 Jan 2015 Ferrara it Beethoven Piano Concert no.1, no.2 & no.5
39.27 Jan 2015 Turin it Beethoven Piano Concert no.1, no.2 & no.5
40.28 jan 2015 Pavia it Beethoven Piano Concert no.1, no.2 & no.5
41.29 Jan 2015 Cremona it Beethoven Piano Concert no.1, no.2 & no.5
42.17 Feb 2015 Paris fr Beethoven Piano Concert no.2, no.3 & no.4
43.19 Feb 2015 Paris fr Beethoven Piano Concert no.1 & no.5
44.22 Feb 2015 Boston usa Beethoven Piano Concert no.2, no.3 & no.4
45.23 Feb 2015 NewYork usa Beethoven Piano Concert no.2, no.3 & no.4
46.24 Feb 2015 NewYork usa Beethoven Piano Concert no.1 & no.5
47.03 May 2015 Hong Kong Beethoven Piano Concert no.1 & no.4
48.05 May 2015 Taipei tw Beethoven Piano Concert no.3 & no.4
49.06 May 2015 Tainan tw Beethoven Piano Concert no.3 & no.5
50.08 May 2015 Shanghai Beethoven Piano Concert no.2, no.3 & no.4
51.10 May 2015 Shanghai Beethoven Piano Concert no.1 & no.5
52.12 May 2015 Goyang kr. Beethoven Piano Concert no.1 & no.5
53.14 May 2015 Shizuoka Beethoven Piano Concert no.2, no.3 & no.4
54.15 May 2015 Tokyo Beethoven Piano Concert no.2, no.3 & no.4
55.17 May 2015 Tokyo Beethoven Piano Concert no.1 & no.5
56.18 July 2015 Bodø no Beethoven Piano Concert no.1 & no.4
57.19 July 2015 Bodø no Beethoven Piano Concert no.2 & no.5
58.21 July 2015 Bodø no Beethoven Piano Concert no.3 & fantasia
59.23 july 2015 London uk Beethoven Piano Concert no.1 & no.4
60.24 July 2015 London uk Beethoven Piano Concert no.3 & Coral fantasy
61.26 July 2015 London uk Beethoven Piano Concert no.2 & no.5
![]()
![]()
![]()